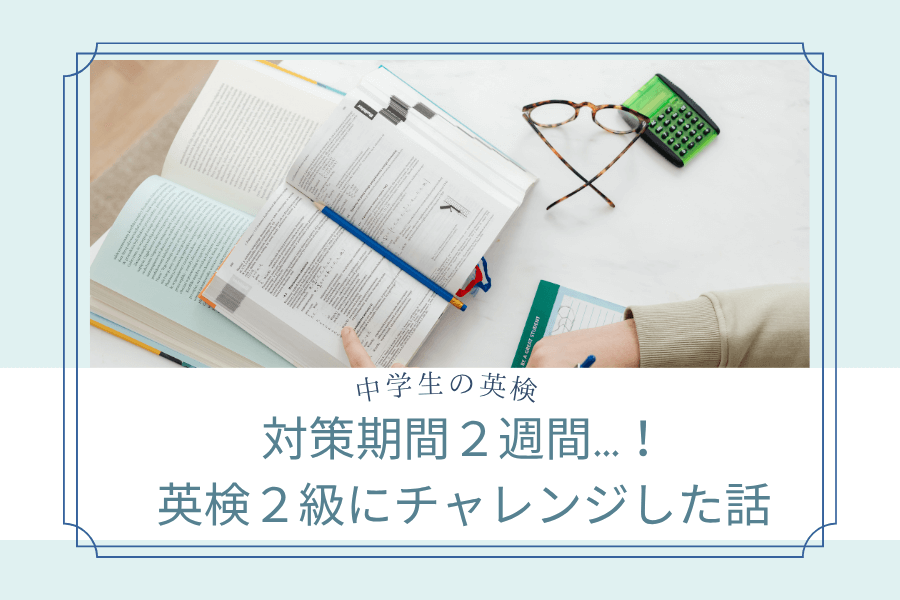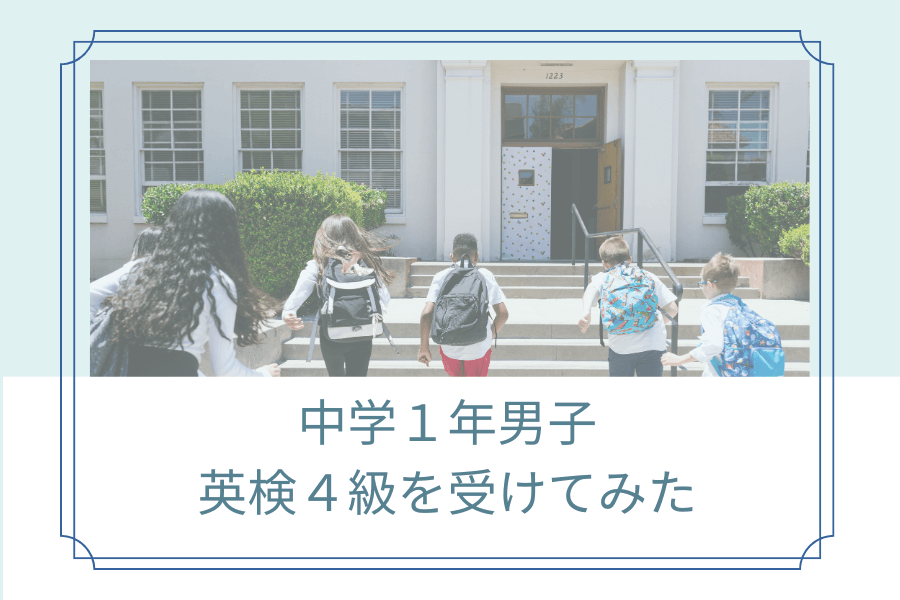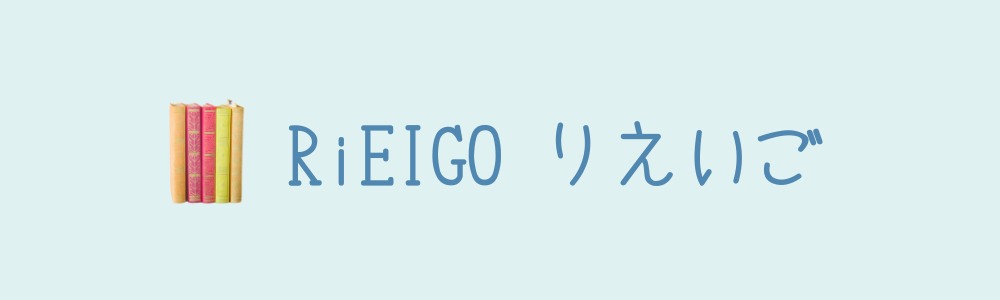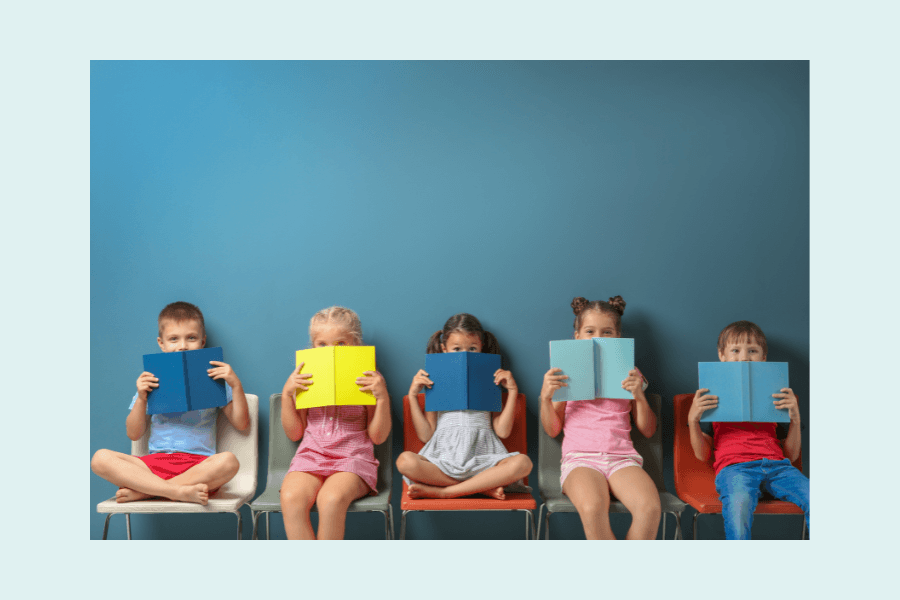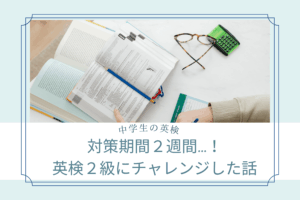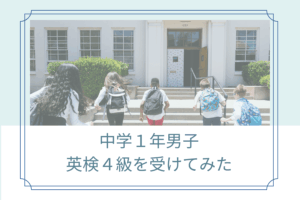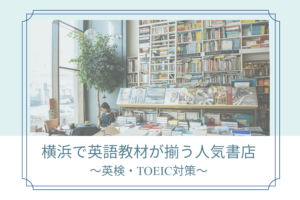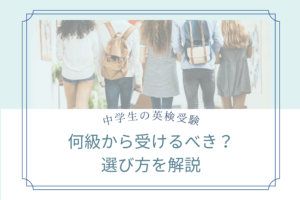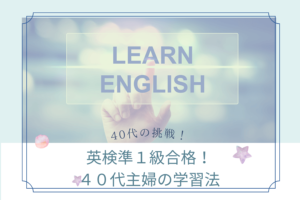悩む人
悩む人準会場で英検を受けるって、どんな感じ?



本会場よりもアットホームな雰囲気です
英検には準会場と呼ばれる小規模会場が存在し、多くは塾や学習教室で試験が行われています。
今回は、我が家の長男が“人生初”となる英検5級を準会場で受けた体験を、母である私の目線からレポートします。想像よりも緊張した本番、見えてきた試験環境のリアル、家庭学習だけでどこまで通用したのか……等身大の受験体験記、どうぞご覧ください!
準会場での英検受験、意外とアクセスも安心だった


いつもの教室じゃないけど、自転車圏内で負担は軽め
準会場といっても、いつも通っている公文の教室ではなく、少し大きめの別教室が会場に指定されていました。最初は「知らない場所だと緊張しそう…」と不安もありましたが、自転車で10分ほどの距離だったため、送り迎えの負担もなく、親子ともに落ち着いた気持ちで当日を迎えることができました。
都市部のように交通の便が良いわけではない地域でも、こうして身近な学習施設が準会場として機能している点は、非常にありがたいですね。
顔なじみの先生が受付に!子どもの表情がほころぶ瞬間
試験会場に到着すると、入口で迎えてくれたのは、なんといつもの公文の先生!まさかここでも会えるとは思っておらず、本人は驚いてしまいました(笑)。そして、緊張で顔がこわばっていたのが、先生の優しい声がけ一つでふっとゆるんだのです。



知ってる人がいるって、こんなに安心感があるんだ…
そんなふうに思わせてくれる一コマでした。初めての試験だからこそ、こうした人とのつながりが子どもの心を支えてくれるのかもしれません。
本番の試験、思った以上に手応えが違った


リスニングでまさかの苦戦…「過去問よりずっと難しい!」
試験が終わって会場に迎えに行くと、長男は少し硬い表情で出口から出てきました。



どうだった?



リスニング、やばい。4割くらいしかわかんなかったかも
実は、本番の2日前に公式サイトの過去問(3回目)を解いたときには、リスニング20問/25問中正解。本人もかなり自信を持っていたはずなんです。
それでも、当日は「音声が聞き取りづらかった」「選択肢が速く流れて混乱した」と戸惑っていた様子でした。模試と本番とでは、やはり会場の音響や緊張感が違うのだと、本人なりに実感したようです。
会場の雰囲気に圧倒された?同じ中学の先輩もいたらしい
また、「思ってたよりも、試験っぽかった」と言っていたのも印象的でした。小さな教室ではありましたが、試験官の指示や静かな空気、鉛筆を走らせる音のなかで、10人ほどの受験生が集中していたそうです。
参加者の中には、小学校低学年くらいの子どももいれば、長男と同じ中学の先輩らしき人もいたとか。年齢や学年の幅があるからこそ、ある種の“本番感”が生まれるのかもしれません。
準会場は問題用紙が持ち帰れない!親にとっても不安要素
ひとつ盲点だったのは、準会場では当日に問題用紙を持ち帰ることができないこと。これ、地味に不便なんです。
「自己採点ができない」というのは、親にとっても子どもにとっても“モヤモヤ”のもと。リスニングが不安と言われても、どこがどう難しかったのか、どの選択肢を選んだのかもわからないため、問題用紙が返却されるまでただただ待つしかありません。
家庭での英検対策、最低限でもここまでできる!
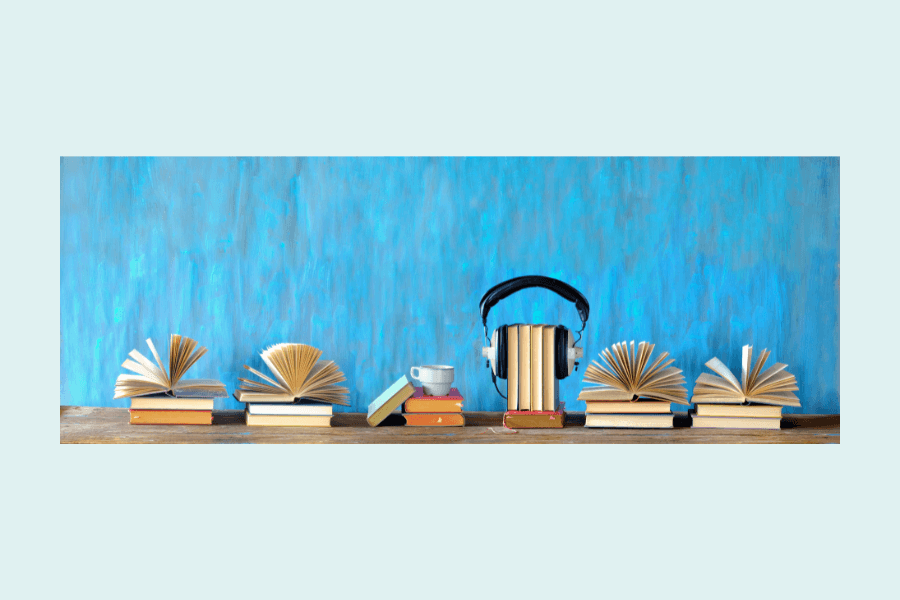
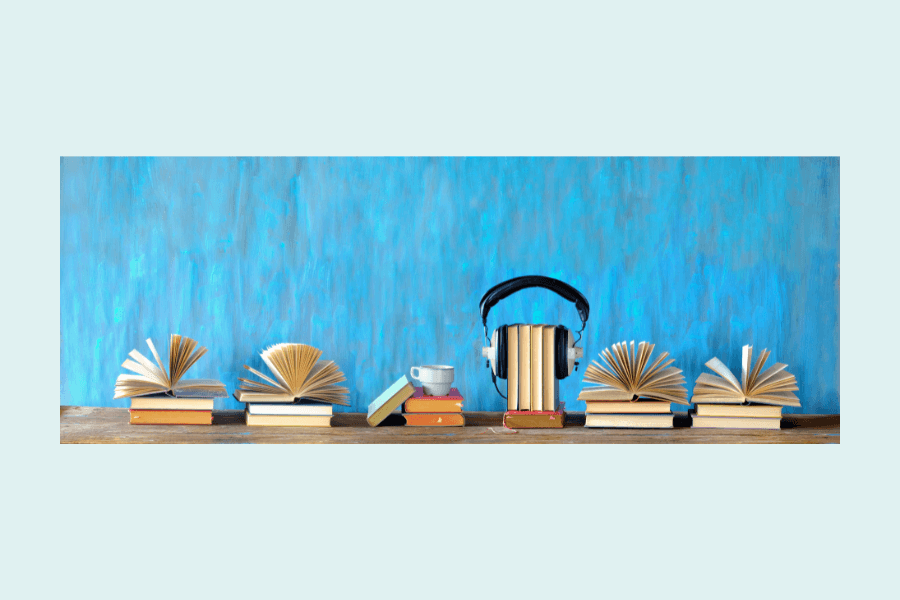
教材は公文と公式サイトだけ!市販テキストゼロでも8割以上
今回の英検対策、実はかなりシンプルでした。使ったのは、公文で学んだ教材と、英検公式サイトに掲載されている過去問(3回分)のみ。市販の参考書や単語帳などは一切使っていません。
公文では「GⅡ(中学1年生レベル)」まで修了していた長男。過去問ではリーディング21問/25問、リスニング20問/25問と、かなり安定した成績を残していました。
本番でリスニングに苦戦したのは想定外でしたが、基本的な英語の読み書きや語彙力は、家庭学習でもしっかり身につけられることを実感できました。
親の役割は、勉強の手伝いより“そばにいる安心感”
当日、私はというと「先に帰らないで。迎えに来て」と言われたこともあり、近くの公園を1時間ほど散歩しながら、アプリでTOEIC対策の「金フレ」を聞いていました。歩きながら単語を覚えるのって、意外と集中できるんですよね…!でも1時間も歩いたら、さすがにヘトヘト(笑)。
試験終了後、ちょっと自信なさげに疲れた様子で会場から出てきた長男を見て、「やっぱり迎えに来てよかった」と改めて思いました。付き添い=サポートではなく、そばに“いるだけ”でも、子どもは落ち着いて試験に臨めるのかもしれません。
長男にとって初めての英検は、単なるテスト以上の経験になったと思います。
自分の力で挑んでみて、思ったようにいかなかった。これもひとつの経験。
準会場での受験はアクセスも良く、比較的少人数で行われるため、初めて英検を受ける子どもにはおすすめの選択肢かもしれません。まだ結果はわかりませんが、この経験そのものが、次の学びにつながると思っています。